 (※イメージ画像)
(※イメージ画像)
日本には充実した公的医療保険制度がありますが、それでも「医療保険」への関心が高いのはなぜでしょうか?公的保険でカバーされるのは治療費の一部であり、自己負担分や差額ベッド代、先進医療費などは別途必要になる場合があります。また、入院中の雑費や収入減も心配です。民間の「医療保険」は、こうした公的保険だけではカバーしきれない経済的負担に備えるためのものです。この記事では、民間「医療保険」の必要性、基本的な保障内容、選び方のポイントを分かりやすく解説します。
【目次】
- なぜ必要?公的医療保険と民間医療保険の役割分担
- 医療保険の基本保障:入院・手術給付金とは
- 知っておきたい特約:先進医療・がん・三大疾病など
- 医療保険の種類:定期タイプと終身タイプ
- 後悔しない医療保険の選び方のポイント
- 【まとめ】
なぜ必要?公的医療保険と民間医療保険の役割分担
日本に住む私たちは、原則として全員が何らかの公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)に加入しており、病気やケガで医療機関にかかった際、医療費の自己負担は原則1~3割に抑えられます。さらに、1か月の医療費が高額になった場合には「高額療養費制度」があり、自己負担額には上限が設けられています。
このように手厚い公的医療保険があるにも関わらず、なぜ民間の医療保険が必要と考えられるのでしょうか。それは、公的医療保険だけではカバーしきれない費用や、想定外の出費が発生する可能性があるためです。
具体的には、以下のような費用が挙げられます。
- 医療費の自己負担分: 公的保険適用でも1~3割は自己負担。高額療養費制度を使っても、一定額の負担は発生します。
- 公的保険適用外の費用:
- 差額ベッド代: 個室や少人数部屋を希望した場合にかかる費用。全額自己負担です。
- 先進医療の技術料: 公的保険の対象外となっている先進的な医療技術にかかる費用。数百万円以上になることもあります。
- その他(入院時の食事代の一部、診断書作成費用など)
- 治療以外の費用: 入院中の日用品費、家族のお見舞い交通費、一時的な収入減少など。
民間の医療保険は、これらの公的医療保険の「穴」を埋め、万が一の際の経済的な負担を軽減し、安心して治療に専念できるようにするための備えなのです。
医療保険の基本保障:入院・手術給付金とは
民間の医療保険の最も基本的な保障は、「入院給付金」と「手術給付金」です。
- 入院給付金: 病気やケガで入院した場合に、入院日数に応じて支払われる給付金です。「入院日額5,000円」「入院日額10,000円」のように、契約時に設定した日額が支払われます。ただし、1回の入院あたりの支払日数(例:60日、120日など)や、通算での支払日数(例:1095日など)には上限が設けられているのが一般的です。最近では、日帰り入院(入院基本料の支払いが必要な場合など)から保障される商品も増えています。
- 手術給付金: 病気やケガの治療のために所定の手術を受けた場合に支払われる給付金です。支払い額は、「入院給付金日額の〇倍(例:10倍、20倍、40倍など)」といった形で手術の種類に応じて設定されているタイプや、手術の種類にかかわらず一律の金額が支払われるタイプなどがあります。入院中の手術だけでなく、外来(日帰り)での手術が保障対象となるかも確認ポイントです。
これらの基本保障が、医療保険の土台となります。入院給付金日額をいくらに設定するかが、保険料や保障の手厚さを決める重要な要素となります。
知っておきたい特約:先進医療・がん・三大疾病など
基本保障に加えて、任意で付加できる「特約」によって、医療保険の保障内容をカスタマイズできます。ニーズの高い主な特約には以下のようなものがあります。
- 先進医療特約: 公的医療保険の対象外である「先進医療」にかかる技術料実費(上限あり)を保障します。技術料は高額になるケースもあるため、付加を検討したい特約の代表格です。保険料は比較的安価な場合が多いです。
- がん特約(がん診断給付金など): がんと診断された場合にまとまった一時金(診断給付金)が支払われたり、がんによる入院・手術・通院(抗がん剤治療など)の場合に給付金が上乗せされたりします。がんへの備えを手厚くしたい場合に有効です。
- 三大疾病特約(特定疾病保障特約など): 日本人の死因の上位を占める「がん」「心疾患」「脳血管疾患」で所定の状態になった場合に、まとまった一時金が支払われるなどの保障です。七大生活習慣病など、より範囲を広げた特約もあります。
- 通院特約: 入院前後の通院に対して、通院日数に応じて給付金が支払われます。退院後のケアを手厚くしたい場合に検討します。
- 女性疾病特約: 乳がんや子宮筋腫など、女性特有の病気で入院した場合などに、入院給付金が上乗せされる特約です。
特約を付加するとその分保険料は上がります。自身の健康状態や家族歴、心配な点などを考慮し、必要な特約を厳選することが大切です。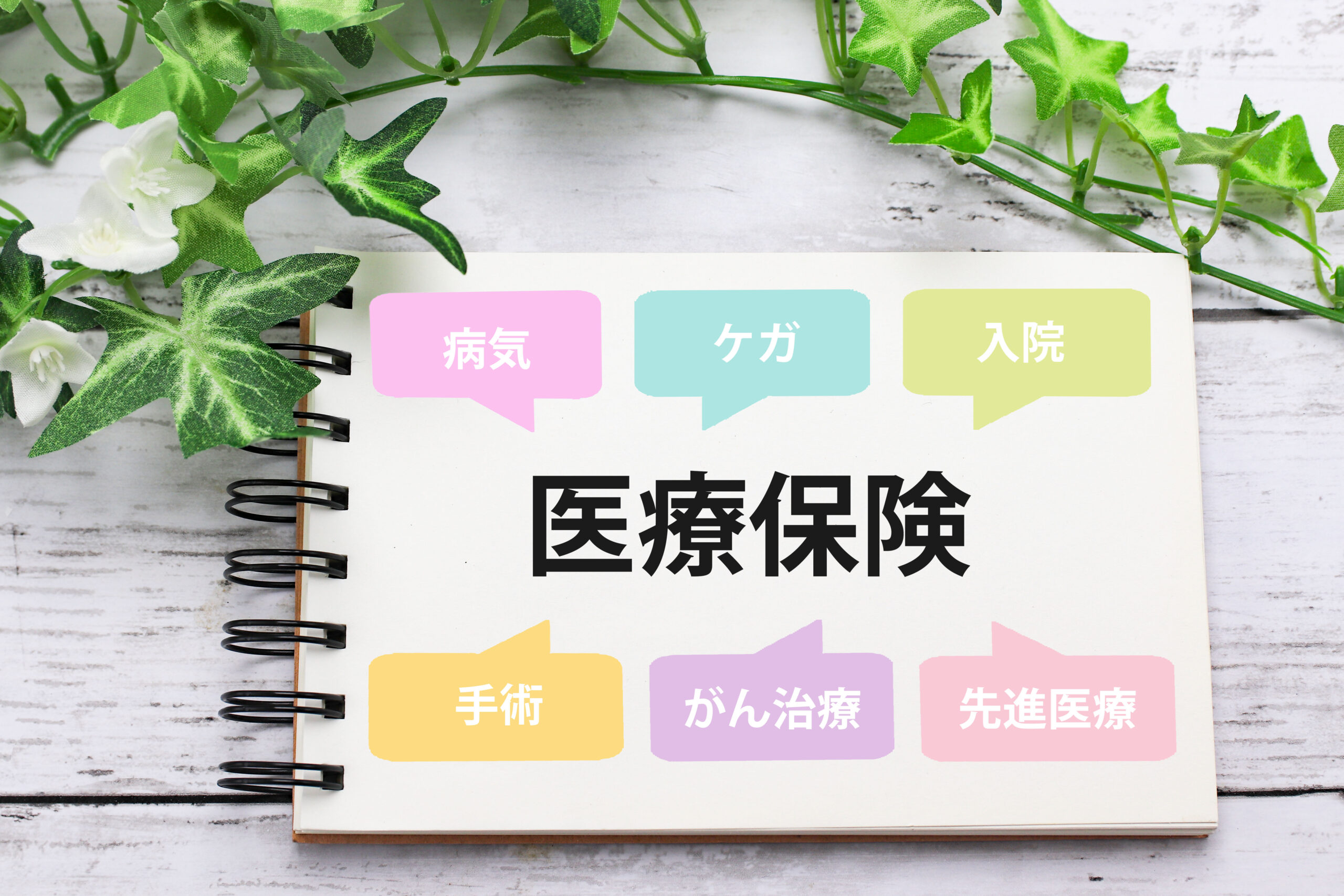 (※イメージ画像)
(※イメージ画像)
医療保険の種類:定期タイプと終身タイプ
医療保険には、保障される期間によって大きく「定期タイプ」と「終身タイプ」の2種類があります。
- 定期タイプ: 保険期間が一定期間(例:10年間、60歳まで、80歳までなど)で定められている医療保険です。
- メリット:加入時の保険料が終身タイプに比べて割安な場合が多い。必要な期間だけ保障を確保できる。
- デメリット:保険期間が満了すると保障が終了する。更新する場合、更新時の年齢で保険料が再計算され、通常は保険料が上がる。商品によっては更新できる年齢に上限がある。
- 終身タイプ: 保障が一生涯続く医療保険です。
- メリット:一度加入すれば、解約しない限り保障が一生涯続く。保険料払込期間(例:60歳まで、終身など)を終えれば、その後は保険料負担なしで保障が継続するタイプもある。高齢になってからの病気リスクにも備えられる。
- デメリット:加入時の保険料が定期タイプに比べて割高になる傾向がある。途中で見直しにくい場合がある。
一般的に、年齢が上がるほど病気のリスクは高まるため、長期的な安心を得たい場合は終身タイプが選ばれることが多いです。ただし、保険料負担とのバランスを考える必要があります。若い間は定期タイプで保険料を抑え、収入が増えたら終身タイプに見直すという考え方もあります。
後悔しない医療保険の選び方のポイント
数多くの医療保険の中から自分に合ったものを選ぶためには、以下の点を押さえて検討しましょう。
- 必要保障額(入院給付金日額)を決める: 公的医療保険の高額療養費制度も考慮しつつ、差額ベッド代や入院中の雑費、収入減などをカバーするためにいくら必要かを考えます。個室を希望するか、現在の収入はどれくらいかなどが判断材料になります。一般的には5,000円~10,000円で設定する人が多いですが、自身の状況に合わせて過不足なく設定することが重要です。
- 保障内容の詳細を確認する: 入院給付金の支払限度日数(1入院あたり、通算)、手術給付金の対象となる手術の種類や支払い倍率、免責事由(保障対象外となるケース)などをしっかり確認します。
- 必要な特約を検討する: 先進医療特約の必要性は高いと言われますが、その他のがん特約や三大疾病特約などは、自身の心配度や家族歴、予算に応じて要否を判断します。
- 保険期間(定期か終身か)を選ぶ: 保険料と保障期間のバランスを考え、長期的な視点で選びます。
- 保険料と家計のバランスを見る: 保険料は長期にわたって払い続けるものです。無理なく継続できる範囲で、必要な保障を確保できる商品を選びましょう。
- 複数の商品を比較する: 同じような保障内容でも、保険会社や商品によって保険料や細かい条件が異なります。必ず複数の商品を比較検討しましょう。保険ショップやファイナンシャルプランナーに相談するのも有効です。
医療保険は、公的医療保険を補完し、もしもの時の経済的リスクに備えるための重要なツールです。ご自身の状況に合わせて、納得のいく保険を選びましょう。
【まとめ】
日本の公的医療保険は手厚いですが、自己負担分や保障対象外の費用も存在します。民間の医療保険は、こうした費用負担に備え、安心して治療を受けるための経済的な支えとなります。入院・手術といった基本保障に加え、先進医療やがんなどの特約、保険期間(定期・終身)などを、ご自身のニーズやライフプラン、予算に合わせて慎重に検討することが、後悔しない医療保険選びの鍵となります。複数の商品を比較し、納得のいく備えを準備しましょう。


コメント